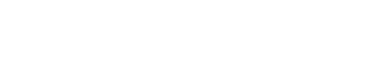2024/06/05
5月31日にNPIウェビナー「台湾頼清徳新政権の誕生とこれからの米中日台関係」を開催しました。
5月20日に、蔡英文氏に代わり頼清徳氏が台湾総統に就任しました。
本ウェビナーでは、台湾新政権の誕生が米中日台関係に与える影響について議論しました。
[パネリスト]
松田 康博(東京大学 教授)
福田 円 (法政大学 教授/中曽根平和研究所 客員研究員)
[モデレーター]
川島 真 (中曽根平和研究所 研究本部長)
当日は、官庁、企業、研究者、マスメディア等の方々の視聴参加を受け、活発な議論が交わされました。議論の主なポイントは以下のとおりです。
・1月の総統・立法委員選挙の結果、民進党が政権を維持したものの、議会で少数与党に転落したため、「弱い民進党政権」が誕生した。
・頼氏は40%強の得票率にとどまったが、民進党に不満を持つ若者の浮動票が民衆党に流れたのが、伸び悩んだ要因とみられる。立法委員については、得票数・得票率いずれも民進党が国民党を上回ったものの、地方・離島に強い国民党が区割りに助けられて第1党となった。
・国民党は次の総統選に向けた有力候補が見当たらず、民衆党も柯文哲氏と黄国昌氏の主導権争いに陥るなか、このまま三つ巴の状態が続けば、頼氏が岩盤支持層に支えられて、次回総統選で再選され、民進党政権が16年続く可能性もある。
・5月20日に頼総統の行った就任演説は、中台関係の現状を反映したものであり、台湾市民には違和感なく受け止められたが、中国は強く反発した。
・演説では、「現状維持」を踏襲しているものの、前提となる「現状」そのものが変化している。蔡政権における現状は、馬政権時に築かれた安定した中台関係であったが、頼政権では、蔡政権時に悪化した中台関係が現状となっている。
・演説は、蔡政権で使われた「中華民国台湾」ではなく、「台湾」という呼称を前面に打ち出して、中国離れを印象付けるものであった。中華民国が、孫文の辛亥革命ではなく、1949年に始まったとの印象を与える歴史認識もそれを裏付ける。
・さらに演説は、過去の李登輝氏の演説をアレンジして台湾独立を暗示し、蔡英文氏の提唱した「四つの堅持」のうち「互いに隷属せず」を強調し、世界のなかの台湾をアピールするなど、中国側を刺激する内容が目立った。
・経済面では、「台商」の台湾回帰を呼び掛けるなど、今後の対中経済依存度のさらなる低下を予見させるものであった。
・頼政権は、今後4年、内政・中台関係いずれも困難が待ち受けている。
・内政は、民進党が少数与党となったことから、人事・予算・立法で野党に主導権を握られている。第1党の国民党も過半数を確保できなかったことから、第3党の民衆党がキャスティングボートを握っている。先般可決した立法院の権限を強化する法案は、国民党案に民衆党が賛同して強行採決された。これに対して、台湾市民による大規模な抗議デモが発生している。民衆党は、安全保障の分野では、民進党と考え方が近いため、今後柔軟な対応をとる可能性もある。
・中台関係は、蔡政権以降コミュニケーションが途絶した状況が続いている。頼総統の就任演説には、中国側が事前に想定しなかった内容も含まれていたため、中国側が分析に時間を要して反応に時差が生じた可能性もある。また、軍事的威嚇は準備されていたことではあり、また実弾演習は台湾周辺では控えられた。台湾市民も、軍事的威嚇を冷静に受け止めており、台湾株価も上昇した。
・中国は、習近平主席が就任してから、鄧小平氏以来積み上げてきた対米協調、台湾平和統一路線を転換し、急速な軍拡により台湾を武力統一する能力を獲得しつつある。米中関係は悪化し、台湾に対する軍事力・経済力を背景とした高圧的対応は、香港における一国二制度の終了と相まって、交渉による台湾平和統一を絶望的にした。習政権の打ち出す政策は、個別の政策が相互に効果を打ち消し合うような矛盾を抱えており、全体として柔軟性と戦略性が欠如しているようにみえる。
・今後も、中国が軍事的威嚇に加えて、経済的威圧や認知戦などを総動員して新政権に揺さぶりをかけることが想定される。次回4年後の総統選までに武力行使に踏み切る可能性は低いが、引き続き野党を側面支援して政権交代を目指すものとみられる。前回の総統選で民衆党支持に回った若者が認知戦のターゲットとなりうるが、先日の抗議デモで警戒感が示されたように、「反民進=反独立」ではない点には留意が必要である。
・総統就任式に、米国からはポンぺオ元国務長官が出席し、ブリンケン国務長官の祝賀メッセージも寄せられたが、これに対して、中国側は国連総会決議2758号を持ち出し、「強烈な不満」を表明した。頼総統の就任演説が、事前に米国側と擦り合わせた「陰謀」だったとの主張まで展開された。
・米国は中国に対して、「一つの中国」政策の維持を表明しながら、実態は大きく変化している。議会で台湾関連法案を可決して、台湾支援を拡充したことにより、対ウクライナとは異なり、大統領権限で、米軍の武器を米国の予算で、台湾に迅速に移転することが可能となっている。米軍は台湾の軍隊の訓練も行っており、特殊部隊の隊員が台湾に駐留するなど、事実上の同盟関係ともいえる。台湾支援については、議会超党派の合意が形成されているため、11月の大統領選には左右されないと考えられる。但し、トランプ氏は微妙な東アジア情勢についての認識が薄いとされる。先日、「もし中国が台湾を侵略した場合、北京を爆撃する」とのトランプ氏の発言が報じられている。
・日本については、過去最大規模の議員団を派遣し、故安倍首相夫人も就任式に出席した。頼総統が、多忙ななか時間を割いて、それぞれと面会するなど厚遇ぶりが目立った。これに対して、駐日中国大使は、「中国の分裂に加担すれば、日本の民衆が火の中に巻き込まれる」との発言を行い、日本側の反発を招いている。
・日本の今後の役割として、日米同盟を軸に対中抑止力を維持・強化しつつ、中国による台湾の孤立化を議員外交等により緩和することが求められている。
・「台湾有事は日本有事」との認識は台湾でも浸透しており、頼政権の日本に対する期待は大きい。日本と台湾が連携して、中国に対してメッセージを発出することも重要である。
・中台間の緊張を巡っては、米中・日中それぞれ首脳対話等を使って、地域安定に向けて適切に管理していくことが必要である。
以 上