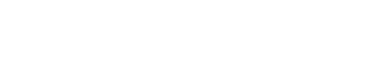2025/09/18
9月12日にNPI公開ウェビナー「認知戦オルタナティブ」を開催しました。
中曽根平和研究所は、9月12日に、一田和樹氏(新領域安全保障研究所)をお招きし、NPI公開ウェビナー「認知戦オルタナティブ」を開催しました。
本ウェビナーでは、中曽根平和研究所の研究プロジェクト「東アジア国際問題の内在的考察:地域研究から見る朝鮮半島・台湾海峡問題」のロシア研究会リーダーの廣瀬陽子が司会として参加し、活発な議論が交わされました。
〔登壇者〕
一田 和樹 氏(新領域安全保障研究所)
〔司会〕
廣瀬 陽子 当研究所上席研究員(慶應義塾大学総合政策学部教授)
議論された主な論点は以下のとおりです。
- 認知戦オルタナティブは、個別の事例に囚われず包括的・俯瞰的・横断的に捉えるものであり、既存の調査研究の成果や事例を組み合わせることで全体像を描き出そうとする試みである。
- 偽情報や誤情報は本質的な問題ではない。そのため、多くの場合、偽情報や誤情報を排しても同じ問題が発生する。
- 認知戦の影響は検証されていない。干渉の事実は確認されているが、その効果は検証されていない。
- 現在までに行われた対策には根拠がなく、成果を期待することができない。効果のない対策に人と予算を割くことは、それだけでマイナスの影響である。実際、この領域にもっとも予算を投下してきたアメリカは悪化の一途をたどっている。
- 攻撃内容よりも攻撃対象と影響が問題である。既存の多くの調査は事例研究が多く、特定の攻撃に焦点を合わせている。一方、その攻撃の対象や効果についてはほとんど調査分析されていないが、社会への脅威としては対象と効果の方が問題である。
- 認知戦の影響は検証されていないが、メディア・政治家・専門家によって過大に評価されている傾向がある。
- 偽情報や誤情報そのものよりも、「偽情報や誤情報は社会の脅威である」、「ロシアのデジタル影響工作が行われていた」と発表することで、情報への不信感、警戒感が広がることをパーセプションハッキングと呼ぶ。これは「不信感」を拡散する戦略であり、社会に警戒主義を広げ、民主主義や社会制度への疑念を深める。
- 日本は国内外からの干渉に弱く、中露など海外からの干渉に過剰に反応するメディア・政治家・専門家はその干渉に利用されやすい。
- 参院選や能登地震ではメディア・政治家・専門家が根拠のないリスクを喧伝したため、国民に過剰な警戒心が植え付けられ、実態が検証されていないリスクに対応するための対策が行われている。
- ファクトチェックは必ずしも効果的ではなく、場合によっては偽・誤情報をかえって拡散させる逆効果を招くことがある。
(なお、有効な対策として、公衆衛生モデルやカナダの中国からの選挙干渉に関する最終報告書が紹介された)