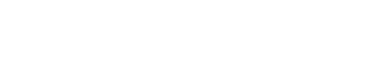2025/01/21
12月18日にNPIウェビナー「技術革新と情報空間のリスク:偽情報と認知戦の最前線」を開催しました。
現代の戦争の戦い方を象徴する"ハイブリッド戦争"では、情報操作によって社会を撹乱し弱体化させることを目的として、平時から情報戦が行われています。偽情報の流布だけでなくサイバー攻撃と組み合わせた認知戦が展開されている現状を踏まえて、進化を続けるサイバー攻撃の手法、人工知能(AI)による偽情報の生成、SNSプラットフォームやデジタルインフラ上の新しい問題、プラットフォーマーによる情報戦への対応等、さまざまな最新動向を新進気鋭の若手研究者と議論を行いました。
1.日時
2024年12月18日 10:00~11:30
2.登壇者(敬称略)
〔パネリスト〕
土屋貴裕 京都先端科学大学経済経営学部准教授
長迫智子 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)サイバー情勢研究室研究員
布施 哲 株式会社国際社会経済研究所(IISE) 特別研究主幹
持永 大 芝浦工業大学システム理工学部サイバーセキュリテイ研究室准教授
川口貴久 東京海上ディーアール株式会社ビジネスリスク本部兼経営企画部主席研究員、マネージャー
〔モデレーター〕
大澤 淳 中曽根平和研究所主任研究員、情報空間のリスク研究会リーダー
当日は、官庁、企業、研究者、マスメディア等から多くの視聴者を受けて活発な議論が交わされました。各委員による発表と議論の主なポイントは、以下の通りです。
■土屋貴裕氏 「中国の認知戦」
・近年、米国の調査から、中国は大規模なボットネット「スパムフラージュ」作戦を展開していることが明らかになっている。受け手の感情的な反応や信用を獲得しやすい生成AIやディープフェイク技術も活用して、対象国の知識人層や将来のエリート層に中国独自の歴史観や政治認識を浸透させつつある。
・中国による認知戦はサイバーインテリジェンス活動と表裏一体である場合が多く、ハッキングによって獲得した対象国や人物に関する機密情報を恣意的に編集して拡散するほか、事実と虚構を混在させた「ハイブリッド暴露」を通じて、受け手が情報の真偽を判別しにくい環境をつくっている。
・日々拡散される偽情報のファクトチェックには限界がある。国民向けの認知リテラシー教育等も重要だが、即効性は期待しがたい。認知戦の対象国は防御にとどまらず、カウンター・ナラティブの発信など積極的に戦略的コミュニケーションを確立する必要がある。
■長迫智子氏 「ロシアの情報戦・認知戦を巡る動向」
・近年のロシアは、AIで生成した多言語のSNS投稿を発信する政治的なボット、フェイクのウェブメディア、ファクトチェック機関の悪用といった手法により自国に有利なナラティブを拡散し、他国の選挙活動を対象に影響工作を展開している。
・ロシアの認知戦戦略は、 (1)相手国の情報インフラから個人の心理、認知領域まで射程にした「情報対立」、(2)情報戦に使う技術や手段としての「情報兵器」、(3)相手の意思決定過程における世界認識上の重要な要素を変更して自国に有利な意思決定を導く「反射的コントロール」の3つに大別される。中でも、人の信念や価値観への説得的影響力が重視されている。
・ロシアは偽情報・フェイクニュースとサイバー攻撃を組み合わせたハイブリッド型の情報戦・認知戦を展開している。近年、「機能妨害型」「情報窃取型」「情報操作型」のサイバー攻撃が組み合わさった事例が増加しており、サイバーセキュリテイと情報戦・認知戦の一体的な備えが必要である。
■布施哲氏 「マイクロターゲティングとデータの武器化」
・デジタル技術の発達により、認知戦の対象は個人にも及ぶようになった。個人の属性や趣味等の詳細なデータを使った「マイクロターゲティング」と言うネット広告の手法が、認知戦や諜報活動にも応用されるようになったからである。
・米国では2015年、ハッキングによって2100万人もの連邦職員のビッグデータが流出した。当時は大量のデータが流出しても、まだ個人の脆弱性を突いた脅迫や協力者(スパイ)の獲得等の影響工作が可能なほどのプロファイリング技術は無かったが、AIの登場でビッグデータの解析が進み「データの武器化」が実現している。
・「マイクロターゲティング」によって、自国の大事な意思決定や世論形成に負の影響が及ぶリスクが飛躍的に高まった。いかに個人データを保護するかは極めて重要だ。しかし、それだけに目を奪われず、個人情報に該当しないビッグデータを戦略資産として活用することも大切だ。
■持永大氏 「権威主義とデジタルプラットフォーム」
・中国における情報通信技術は、自国の安全保障の強化、経済的発展、政治的安定性の3つの観点から位置付けが高い。中国の社会統治の近代化にも情報通信技術を活用している点は、特筆すべきである。
・情報通信技術と権威主義体制には、相性の良し悪しがある。良い面は、情報の制御によって国民の自由を制限したり、競争環境を統治者に有利にしたり、統治者が国民の選択を思い通りに変えることができる点である。相性が悪い面は、大規模な情報の制御や完全な統制は難しいことだ。個人の独裁体制の場合、例えば中央で意図したナラティブが末端までいくには非常に時間がかかり、末端で手が加えられたら変容したものが拡散する。中央に君臨するたった一人の制御に狂いが生じれば全体に影響を与える、単一障害点となる。必ずしも、情報通信と権威主義体制は相性が良いとも言えない。
■川口貴久氏 「デジタルプラットフォーム規制の現在地」
・民主主義国家において、デジタルプラットフォーマー(DP)は大きな社会的影響力を有しているにもかかわらず、ガバナンス、透明性、予見可能性が不十分であると批判されている。そのため、各国政府は様々なアジェンダ(競争関連、コンテンツモデレーション、メディア保護、個人データ移転規制等)でDPの規制を制定・執行している。
・規制の考え方・あり方は米国、欧州、中国等で大きく異なる。欧州は最も強力な包括的DP規制として、デジタル市場法(DMA)とデジタルサービス法(DSA)という二つの規制を設けている。米国ではバイデン政権当時、反トラスト法が執行された。しかし、欧州型のDP規制は必ずしも民主主義社会の普遍的なモデルではない。例えば、韓国や台湾がそれぞれ欧州型のDP規制を模倣しようとしたが、断念している。
・日本では公正な競争環境整備と偽情報対策に関して、DPの「自主的取り組み」を標榜する欧州的なアプローチがとられると見られる。
■パネリストのプレゼンテーションの後、モデレーターの大澤座長から以下の質問が投げかけられ、パネリスト間で議論が行われました。
1.中露両国の情報戦・認知戦における協力の現状について、どのように考えるか。
両国の軍事関係者が、情報戦・認知戦の手法について情報を交換し合っていることが確認されている。近年、ロシアがインフルエンサーを用いた対外影響工作を行っているが、これは中国の手法を模倣したものである。欧州では中露のインテリジェンス機関が協力して諜報活動/情報工作を行っており、対象国にとっては深刻な状況だ。今後は両国に加えてイランが連携をとる可能性があり、注意が必要である。
2.情報戦・認知戦におけるAIの果たす役割について、どのように考えるか。
生成AIの登場で、日本語を含めた言語障壁が克服され、様々な国に対する影響工作が可能になり、偽情報の生成・拡散速度が飛躍的に高まった。SNS空間では悪意あるコンテンツが検出・削除されることがあるが、生成AIによる情報はこうした検知の回避が可能だ。また、現時点ではまだ発展途上だが、偽情報のファクトチェックを自動化するためにAIを活用する研究も進んでいる。
3.個人として、情報戦に対応するためにはどうすればよいのか。
「我々が日常接している全ての情報には改竄の手が加えられており、誰かの恣意的な解釈がなされた上で公表されている可能性がある」という感覚を身につけることが重要である。「あらゆる情報は主観やバイアスの影響を含む」という前提で情報に接する態度が必要だ。世の中の事象は複雑なので、簡単で分かりやすい情報には注意を払うべきである。誰しも、無意識のうちに偽情報の拡散に加担してしまうリスクがあることも留意したい。接した情報をむやみに拡散する前に、一歩立ち止まる勇気をもつことが必要である。