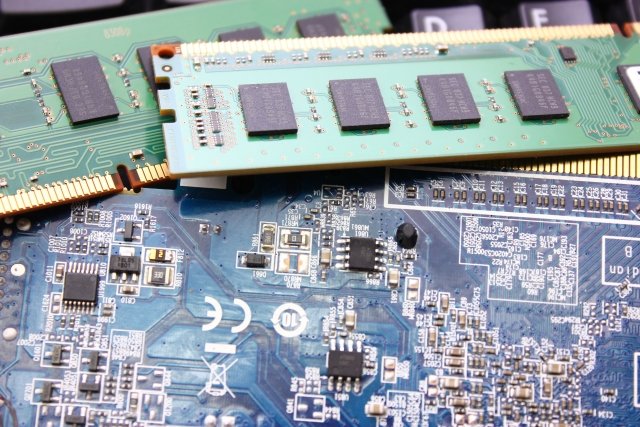2021/01/25
「デジタル時代の金融・政治経済をめぐる安全保障基盤とは?」【下・丁々発止編】(中曽根平和研究所「デジタル技術と経済・金融」研究会)
中曽根平和研究所では標題につき、西村陽造研究委員(立命館大学政策科学研究科教授)ならびに、坂本正樹研究委員(丸紅経済研究所エコノミスト)との意見交換を、以下の通り開催しました。
【上・プレゼン編】に続き、【下・丁々発止編】の2回に分けて、概要をお届けします。なおスクリプトはこちらをご覧ください。
1 議論
■主な論点1: 経済安全保障をめぐる見方・考え方
○経済安全保障の概念は第二次世界大戦以前から変わらず存在するもので、対象が、石油、技術規制、レアアース、デジタル・サイバー・宇宙と変わっていくものという理解。
なお、米中関係については今後、必ずしも対立関係で続かない可能性がある。バイデン次期政権に中国がアプローチする姿勢も見えているなかで、注意してみていかなければならない。
〇従前より欧米中露とも、安全保障の概念においては軍事がトップにあり、そしてその強い軍事を支える強い経済、それらを支える強い技術、という概念でアクションを取っている。近年の米中対立のそれぞれの打ち手も、この構図で見ると、10年後の軍事実用化・軍事覇権を見据えたものと理解できる。
しかし平和国家・日本では、この構図が必ずしも見えておらず、特に民間企業からは経済安全保障・技術管理等に対する不満も出てきやすい。もう少し日本政府も日本企業も、軍事安全保障と経済安全保障を並行して考えていく必要が出てきているのだろう。そして、むしろこの経済安全保障の高まりによる、世界経済の不透明性・リスクの高まりにどう向き合って(この環境をどう味方にして)、日本企業も自社の利益を最大化していくか、という戦略も必要ではないか。
〇かつての輸出管理体制強化の事例を見ると、中国のレアアース規制にしても、約50年前の石油危機に関しても、むしろ輸入国のレジリエンスを高める方向に動いている。そう考えると、経済安全保障の諸手法については、その目的と手段の対応がしっかりしているかどうかを見極めながら、慎重に活用すべきものと感じる。
〇企業にしても、大学にしても、やはりある国家に本拠を置かざるを得ない。そうしたなか、その国家の方針・政策が、グローバリゼーションであったり、また経済安全保障であったりという側面において、企業・大学に強く影響を及ぼしうることを改めて感じる。
〇中国が人民元の国際化を明確に打ち出したのは、現在の習政権になってからだ。おそらくは米国・米ドルへの挑戦ということを明確に意識していると感じる。一方で、国民(居住者)の管理体制を重視しているが故に、人民元を国内外自由に使わせないような政策もとってきている。
これらを踏まえると、自国が管理・制御できるという前提を満たす取引の範囲で、国外の非居住者による人民元の使用の拡大を図っていくのではないか。
なお人民元の国際決済における使用は、中国経済の台頭のなかで趨勢的に拡大してきたが、当局の資本規制強化によって一時的に減少した局面もあり、一本調子で拡大してきたわけではない。
〇日本においては、デジタル時代の経済安全保障とともに、デジタルそのものの安全保障の議論も必要と感じる。
昨今のサイバー化、デジタル化を進めるうえで、いざという時への備えが、サイバー技術、デジタルサービス、データの3つの面で必要だろう。この3つのそれぞれについて、フルに他国依存したり、国内活動主体をゼロにしたりしないための「政府・企業の取り組み」が重要ではないか。経済原則だけで動かない部分を一定程度確保すること、同時に、それに関わる人材を最小限でもキープすること、など。
〇米国の政府クラウドにおける民間ベンダー選定プロセス(マイクロソフトが受託)からも感じるように、民間企業にデジタル基盤を依存せざるをえないなかで、どういったリスクを考慮して、対処し、選択していかなければならないのか、といったところがあると感じる。日本もこういう点で、政策対応的な遅れをとってはならない。
■主な論点2:デジタル時代の企業にとっての経済安全保障リスクとレジリエンス
○もし仮に米ソ冷戦時のような世界二極化・ブロック化、そしてそれに基づく陣営ごとの輸出管理体制ができるとするならば、これはある意味、完全なデカップリングであり、確立された可視的な分かりやすい世界だ。グローバルサプライチェーンの困難さは増すが、それが明確になるという意味で企業のビジネスリスクも低減するといえるだろう。
とはいえ、そういったシンプルな世界とはならず、それ以前のところで、おそらく様々な動きがあり、そこで企業にとっても、関連周縁各国にとっても、グローバルサプライチェーン維持と再構築とのバランスが試され続けていくものと感じている。
〇経済安全保障含めた世界経済の不透明性・リスクの高まりに対しては、リーマンショック後、そしてコロナからの経済回復にしても、設備投資の回復の度合いが日本企業は米欧に比べておしなべて弱いところがある。
今回については、資金繰り問題やコロナ禍前からの景気の強弱の差もあるものの、世界経済の不透明感が、より重しになっているようにも感じる。ただ、年初の第三次補正予算では、デジタル関連やグリーン関連の促進策が盛り込まれた。これらが不透明下での日本の経済成長をリードする材料になっていくと感じている。
■主な論点3:技術革新と金融システムの安定的発展
〇複数基軸通貨体制のメリットデメリットについて。基軸通貨国の間で牽制し合うことで健全な経済運営を促す効果がある一方で、基軸通貨の間で資金シフトが起こることで世界経済を不安定化させる懸念がある。
なおユーロについては、通貨危機で明らかになった「財政統合なき不完全な通貨統合」に起因する問題を解決するための政策運営的な取組みが優先されるだろう。国際通貨としてのプレゼンスが高まるとすればその結果だ。
また日本円については、GDPの世界に占める比率が現在の5~6%程度からさらに下がることを考えると、基軸通貨となる可能性は低いが、それでも有力な国際通貨としての地位は続くだろう。従って日本としては、ドルを基軸通貨とした世界の中での国際通貨の立場を維持するためにも、基軸通貨としてのドルをいかに支えるかが課題と感じる。
〇中央銀行と民間金融機関の基本的な枠組みが今後変わらないとしても、一方で、デジタルをうまく使いこなすかこなさないかで、国ごとの金融システムの差が出るのではないか、という漠然としたイメージを持っている。
〇中央銀行デジタル通貨(CBDC)が国際金融システムの安定性を変える影響は小さい可能性がある。それは以下の理由による:
①デジタル通貨の時代になっても、ファイナリティー(決済手段の支払完了性)のある決済手段は現金と中央銀行預金で、CBDCには保有上限が設定されると見ていること。
②デジタル技術が進んでも、国際金融システムは人間が運営するものである以上、その不安がなくなることはないと見ていること。
従ってデジタル時代に於いても、その安定性維持にふさわしい金融システムの制度設計が必要。
一方、世の中全般では、CBDC利用の広がりに期待する見解も多い。価値の安定性を踏まえ、また銀行業界の状況も鑑み乍ら進める中で、資本取引を自由化すれば、将来的にある程度ブロック通貨に成長していく可能性についても、引き続き考察可能。
〇CBDCに求められる処理速度について。クレジットカード世界最大手のVISAは、1秒間に数万件の処理をこなしていると聞いたことがある。おそらく、デジタル通貨の決済については、特に基軸通貨のそれは、これを上回る処理能力が必要になるだろう。ビットコインなどに導入されているブロックチェーン技術の現在の処理能力では遠く及ばないと捉えている。
〇デジタル通貨の運営主体については中央銀行以外にも様々な可能性が考えられるが、徴税権や警察・軍事力を背景とした政府が通貨を発行し、それに基づいて金融システムが出来上がっているという仕組みで考える以上、運営主体がどうであれ、ファイナリティー含めた財産を守ってくれるのは国家という仕組みは変わらないのではないか。
なお中国のように、消費者向け大手民間デジタル決済が広く先行普及する中では、政策当局による棲み分け方針にも注目が集まるだろう。
〇クレジットカード、電子マネー、バーコード決済、ポイントプログラム等々、ファイナリティーのない消費者向けの決済システムやプラットフォームなども世界的に林立するところだが、これらの国際相互運用の方向性は、こうした決済手段間の競争の中で、結果として見えてくることだろう。
■主な論点4:デジタル時代の金融・政治経済をめぐる国際安全保障の調整基盤
○国際安全保障へのリスク検討が高まっていくなかで、その当事者たる国家・企業等を越えた(結び付けた)形での、マルチステイクホルダースキームでの国際調整機能の今後の方向性・可能性について、一例として参考になるのは、G20における、政府とは独立した団体から成るC20(市民団体)、T20(シンクタンク)、B20(経済団体)等のエンゲージメント・グループだ。
こうしたグループは、国際調整機能を担うベースにもなるとも思う一方、一定の強制力を持った調整機関として機能するためには、前提としてグループ内メンバーの協調関係が必要になる。従って、米中を中心に国家間の対立が厳しくなると、企業等の関係もそれに乗じて厳しさを増し協調がますます困難となる懸念がある。
○世界貿易における地域的な取り決めであるFTA・EPAなどのように、国際的なグループ形成が、必ずしもブロック経済に見られるようなゼロサム的な対立を生み出すものばかりではなく、協調によるプラスサムを生みだしていく側面がある。
2019年に日米豪政府間で、インド太平洋エリアを中心とした各国通信インフラの構築支援を行うBlue Dot Networkという構想が打ち出されたが、このように主義主張を同じくするような国・政府系機関が連携をして、他国の投資活動を支援していくといった動きもここに含まれる。
〇日米同盟を基軸で国際関係を進めていく前提で考えるならば、米日の法的ツールの非対称を解消していく工夫が必要と感じる。
業界団体を介した日本政府への要請においても、米国の法的規制の域外規制の問題が指摘されていたが、これも、日本側での法的ツールの整備で補っていくことが出来るものと考える。
○大学の基礎研究はオープンを旨としてきたが、デュアルユース(軍民共用技術)への着目・懸念が高まる中で、基礎研究の多くはデュアルユースに実質関係しうると見ている。
米国では留学生の対応含めて、技術管理を厳しくしている状況があるなかだが、今後の国際的な可能性を考えた場合、国家間での技術関連のコンソーシアム立ち上げなどにより、集団安全保障的に国際的な技術管理フレームワークを作っていく方向性が1つの理想形かもしれない。とはいえ、企業や大学がそこにどう参画し、共通規範を明確にしたうえで、国益(そして身近なメリットと安全性とのバランス)を踏まえた諸議論を通じ、どういう健全な関係性を作っていくかが、チャレンジと感じる。
2 日時等:令和3年1月6日(水)14:00-16:15 (ウェブ会議により実施)
3 参加者: 中曽根平和研究所「デジタル技術と経済・金融」研究会 研究委員、および中曽根平和研究所関係者 ほか