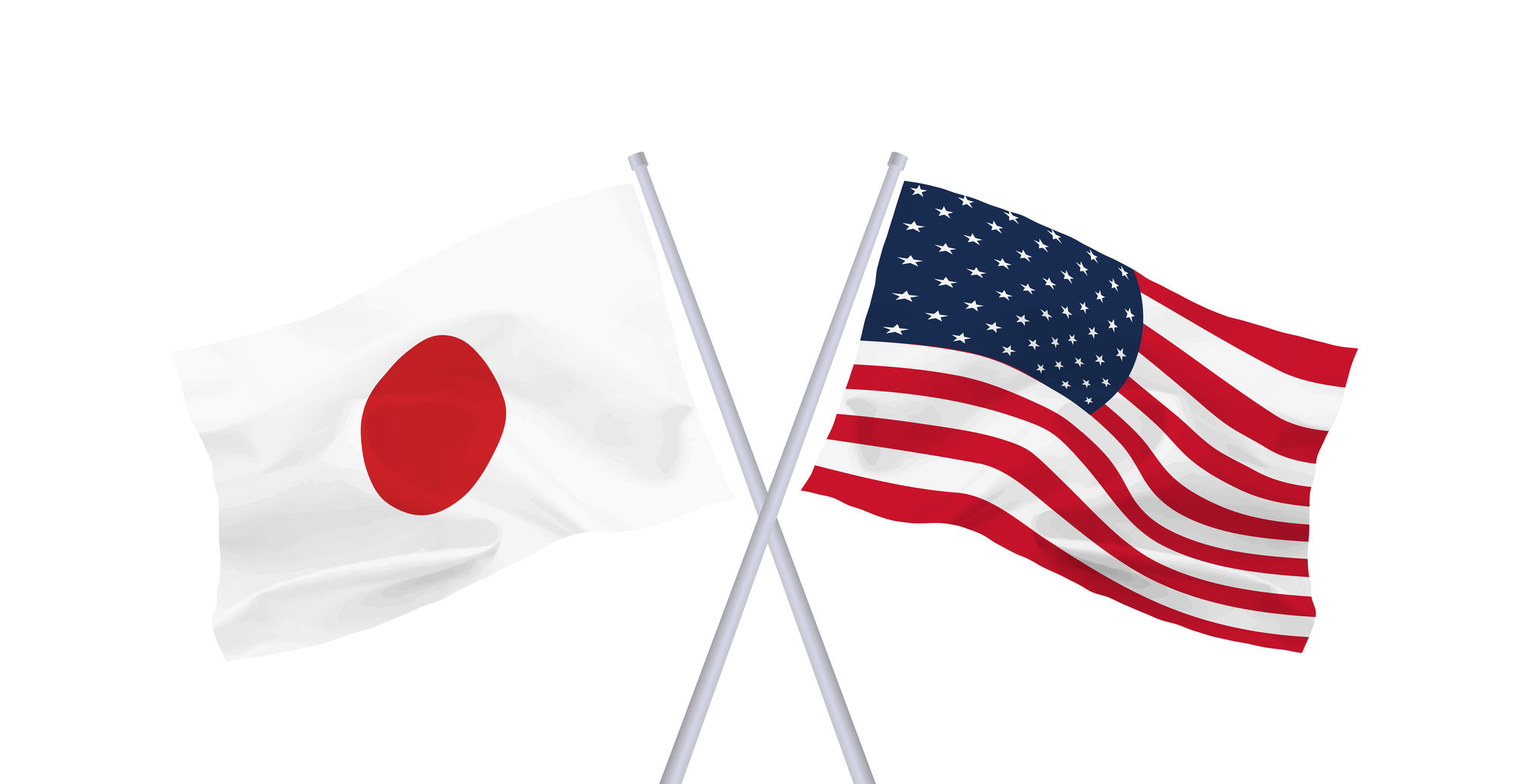2021/03/18
「ミャンマー情勢に想う」(理事長 藤崎一郎)
最初にミャンマーに行ったのは四半世紀以上前の1994年で、SLORCと呼ばれる軍事政権が支配していた。88年のいわゆる「8888運動」を鎮圧した青年将校たちは、自分たちがすべてを切り回しているとあたかも昭和維新の日本の若手軍人を想起させる自負にあふれていた。スー・チー女史は90年の選挙で圧勝したのに自宅軟禁状態にあった。いずれ同女史が復活する可能性もあるのではないかと水を向けると、ミャンマーに長い日本人たちは異口同音に夫君は英国人だし、女史は国民と遊離している、軍人は経済開発にも熱心であり、一般大衆は軍政のもとでの安定を希求していると述べた。疑問を感じた。
受難の指導者と女性後継者
スー・チー復活の情報を私が持っていたわけではない。そう思ったのは二つの理由からであった。一つはアジアでは指導者が政変などで排除されたり志半ばで倒れたりすると妻、娘、妹が戻って来た例が多い。パキスタンのブットー首相、インドのガンディラ・ネルー首相、スリランカのバンダラナイケ首相、タイのインラック首相、インドネシアのメガワティ大統領、フィリピンのコラソン・アキノ大統領、韓国の朴槿恵大統領と枚挙にいとまがない。もちろんこれらの指導者はそれなりに力量があった人もあり、弔い合戦と片づけるのは軽率のそしりをまぬがれないだろう。世界の他の地域でもアルゼンチンのイザベル・ペロン大統領など類似の例がないわけではない。しかし暴れ者のスサノオを放逐して天岩戸から天照大神を引っ張りだしたいというアジア人共通の判官びいきの心情があるように思われた。国民の英雄アウンサン将軍の娘は十分な有資格者だった。
必然でない現在
もうひとつはより本質的な理由である。これはソ連崩壊の感想から来ている。88年頃ロンドンのチャタムハウスでノーベル物理学賞のサハロフ博士の講演を聞く機会があった。サハロフ氏はゴルバチョフのペレストロイカやグラスノスチ改革くらいではソ連は到底立ち行かない、モスクワの子供と違い、ウクライナ地方の農園では子供が炎天下で一日10時間以上働かせられており、不公平に対する不満が鬱積している云々と熱弁をふるった。当時ゴルバチョフはサッチャー首相が「彼となら一緒に仕事ができる」と評価し、英国のみならず国際的に人気が高かった。英国のトップクラスの言論人や外交関係者のサハロフ講演への反応は極めて冷たく、この学者は物理学では優れているが政治というものが分かっていないなという感じだった。
ところがご承知のとおり91年にはソ連が崩壊する。そのとき私はインテリの多くは現実容認派でそれが間違いのもととなることを強く認識した。経緯や実態はともあれ現実に政治や経済が今ある姿は必然であるともっともらしくつじつまをあわせて正当化してしまう。その結果、本当の国民心理を見逃してしまう。たとえばいま米中関係を論じる時に多くの識者は、米国の圧力に中国の国民は強く反発しているとか第三国は両大国の間に挟まって苦悩していると述べる。国民は世論調査で聞かれればもちろんこうした答えをするだろう。安全牌だからだ。しかしこれらの人々に米中どちらの国に居住したいか聞くことができれば答えは自明である。圧倒的に米国行きを希望し中国に行きたい、居たいなどという人はほとんどいないだろう。中国で指導者や政権に対する反発が言えるはずがないのだから聞くだけ野暮である。米大統領選挙についてもトランプが勝てばラストベルトなどの不満が鬱積していたので当然の成り行きと解説し、4年後バイデンが勝てばトランプの行き過ぎに国民が鉄槌を下したとあたかも起こるべくして起こったように説明が行われる。
しかしいずれもていねいに各州の投票数を見れば、接戦州に住むたかが4万人弱が逆に投票すれば逆な結果になったのである。けっして必然というほどではない。ちなみにこの数字は全投票者の0.005%以下である。ミャンマーに戻っていえば国民の多くは、当初から内心は軍政に反発しておりスー・チー女史復帰を希望していたが、政権をおそれ外国人などにかんたんに本心を明かさなかったのだろう。私の話した日本人の多くは仕事を通じておのずと政権と近くなっていたように思われ、国民からは警戒されていただろう。岡目八目ということも大事だと痛感した。
反体制デモと国際世論
次に反体制デモについて触れる。国民の抗議運動が功を奏するのは、いくつかの場合がある。反政権デモが適切な指導者を得て大きなうねりとなる場合、国際世論の圧力が大きく西側諸国の政府も動かし、その結果政権が屈せざるを得なくなる場合、長い年月を経て政治体制が変わり再評価される場合などである。反政権側の指導者に人を得た例は先ず南アフリカのマンデラが浮かぶ。政府との取引に応じず、27年間も投獄されたが耐え抜き、抵抗を貫いて国のトップに立った。ポーランドのワレサ元大統領はじつは裏で共産政権と協力していた云々の情報もあるがやはり一介の民主化運動家から「連帯」をひきいて革命運動を成功させた。国際世論が奏功するのは米英仏などのメデイアが連日大きく取り上げ、これらの国の政府が腰を上げざるを得なくなる場合である。最近ではアラブの春の例が思い浮かぶ。カイロのタハリール広場に市民が集結し一触即発の状況になった。軍部も市民を制止しなくなった。オバマ大統領はムバラク大統領に電話し、ムバラクは鎮圧の自信を示したが、オバマは24時間以内に降板するよう言い渡してその旨発表する。かりにも選挙で選ばれた他国の首脳に対してであり、ずいぶん乱暴な話と思った。
最近出たオバマ大統領の回顧録を見るとそのとき政権内で議論があり、世代が上のバイデン副大統領、ヒラリー・クリントン国務長官らは安定志向で米国の盟友だったムバラクを直ちに切ることには反対、ブリンケン補佐官ら若手は切らなければ世論対策上持たないと意見が分かれ、オバマは後者に与したと書いている。ブリンケンとバイデンがオバマの前で違う意見を述べるという意味で印象に残った。このように米国が切りすてた指導者としてはマルコス比大統領、スハルト・インドネシア大統領、ムシャラフ・パキスタン大統領、カダフィ・リビア最高指導者などがある。これら指導者の多くは米国との関係が生命線であった。これにひきかえロシアも中国も国際世論には一切耳を傾けず断固鎮圧する。たとえばハンガリー動乱、プラハの春、天安門事件などでは政権ないし支配側は徹底弾圧して収めた。ハンガリー動乱、プラハの春は何年もたって政治体制が代わり見直しが行われたが、多数の人はすでに処刑されたり行方不明になったり拷問を受けたり長期の苦役などの辛酸を嘗めさせられた。
勝てば官軍
ミャンマーでの弾圧の程度は承知していないが、国民は自分の将来、生命まで投げうっても独裁者に対抗して立ち上がっている。今の世界で言えば、サウジアラビア政府にトルコで暗殺されたカショギ氏、香港の民主運動家たち、ロシアの野党活動家ナワリヌイ氏らもしかりである。独裁政権の恐れるのは蟻の一穴が政権政体の崩壊につながることであり、喰うか喰われるかの意識だろう。中途半端な妥協はなかなかしない。中国の反日デモのような政権代理人のごとき運動とはまったく違う。かつての日本の学生運動の多くとも異なる。学費値上げ反対のような些事で決起し騒いだが、いわばハシカのような通過儀礼だった。卒業後は、官庁や大企業に就職して嬉々として社畜になっていったのとまったく違うのである。これら各国で決死の覚悟で立ち上がる人々こそが長い目で見ると歴史を変えていく。テロや暴力反対というのは容易いが、じつはその時は暴力、暴徒とみなされたものが、時をへて英雄になっていく例もある。ボストン大虐殺、安政の大獄の犠牲者しかりである。草莽崛起し、勝てば官軍になる。我々の時代では東欧でもベトナム、カンボジアでもこうした例をたくさん見てきた。その一方いまだに弾圧が続いている例も多数ある。
国際世論の圧力の必要
ミャンマーの場合どちらになるか。指導者としてはロヒンギャ問題で国際社会を失望させた面はあるが、国民一般の気持ちはつかんでいるスーチー女史がいる。マンデラ、ワレサにひけをとらない大きな存在である。また、立ち上がっている人に支えとなり得るのは国際世論である。国連安保理は内政不干渉主義の中国やロシアがいるし、ASEANも加盟国の内政には踏み込まないのでいずれも頼みにならない。ミャンマー軍事政権は長い米国の制裁に耐えてきており、国際世論の非難はものともしないというふうを装うだろう。しかし実際は米国からの制裁解除や日本などからの投資増は経済活性化のため大きく評価しているはずである。中国に全面的に依存したいとも思っていないだろう。そこで国際世論がどこまで飽きずに情勢に関心を持ち続けるかが大きい。独裁政権はおおむね時は自らを利すると考えるからである。ロシアのクリミヤ併合、中国の南沙諸島軍事基地建設しかりである。既成事実を積み重ね正当化しようとする。こうした状況に鑑み、日本も日ミャンマー二国間友好という観点だけでなく、より高い見地、幅広い視点からこの問題にきちんと対応していく責任があろう。